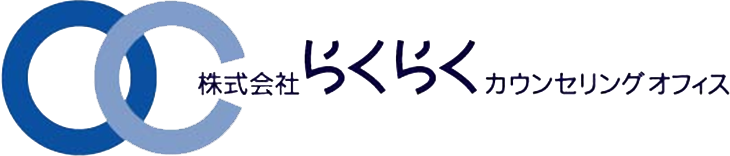春の風に誘われて、ふと空を見上げると、満開の桜が一面に広がっている。その美しさに思わず足を止め、しばらく見とれてしまう――そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。そして、やがて花が散り始めると、なぜか胸が締めつけられるような、少し切ない気持ちになることもあります。なぜ人は、桜の「満開」と「散り際」にこんなにも心を揺さぶられるのでしょうか。この問いには、心理学や脳科学の知見がヒントを与えてくれます。
目次
1. 満開の桜が私たちに与える「快」の感覚
桜が満開になったとき、私たちの脳は非常に活性化しています。特に関係しているのが、「報酬系(Reward System)」と呼ばれる脳のネットワークです。
報酬系には側坐核(nucleus accumbens)や腹側被蓋野(ventral tegmental area)が含まれ、ここではドーパミンという神経伝達物質が分泌されます。ドーパミンは「やる気」や「快感」に関係し、これが放出されると人は「うれしい」「気持ちいい」と感じます。
例えば、2014年にイギリスのロンドン大学(UCL)の研究チームが発表した研究によれば、美しい景色や芸術作品を見たとき、視覚皮質と報酬系が連動して活性化することが明らかにされています(Ishizu & Zeki, 2011)。満開の桜という非日常的な美しさが、私たちの脳にとって強い刺激となり、快の感情を引き起こしているのです。
2. 散り際の桜に感じる「切なさ」の正体
一方、桜が散り始めると、私たちはどこか切なさや、物寂しさを感じることがあります。この感情には、共感力や時間に対する意識が関わっています。
脳科学の視点で見ると、**前頭前野(prefrontal cortex)や島皮質(insula)**といった部位が活動していることがわかっています。これらは「共感」「自己内省」「感情の調整」に関係する部位であり、「この美しさがもうすぐ終わってしまう」という意識が働くときに活性化します。
心理学の世界では、こうした感情は「トランジエンス(transience)=儚さの認識」と呼ばれ、美しいものが一時的であると気づいたとき、人はより強くそれに価値を見出すという傾向があります(Keltner & Haidt, 2003)。つまり、桜が散りゆくさまに「無常」を見出すことで、より深く心が動かされているのです。
3. 「ピーク・エンドの法則」と桜の記憶
心理学者ダニエル・カーネマンが提唱した「ピーク・エンドの法則(Peak-End Rule)」をご存じでしょうか?これは、人が出来事を記憶するとき、「最も印象的だった瞬間(ピーク)」と「終わりの瞬間(エンド)」を中心に記憶する、という法則です。
桜のシーズンは短く、私たちは「満開のピーク」と「散り際のエンド」の両方を短期間で体験します。だからこそ、桜の季節は私たちの記憶に強く残り、「今年も桜を見に行こう」と毎年思うのです。
4. 日本人の文化的感性と「もののあはれ」
さらに忘れてはならないのが、日本人独特の感性――「もののあはれ」という考え方です。これは、平安時代から続く日本の美意識で、「美しいものに宿る儚さに、しみじみと心を動かされる感覚」を指します。
近年の心理学でも、「文化的スキーマ(Cultural Schema)」という概念を用いて、こうした感性の違いが脳の反応に影響を与えることが示されています。たとえば、日本人は欧米人と比べて、季節の移ろいに対する感受性が高く、自然の変化に強く情動反応を示す傾向があると言われています(Nisbett et al., 2001)。
おわりに・・・桜が教えてくれる「今を生きる力」
桜は、ただ美しいだけの存在ではありません。私たちの心に「喜び」と「儚さ」を同時に届けてくれる、特別な存在です。
心理学・脳科学の観点から見れば、桜を見ることで私たちは脳の報酬系を活性化させ、同時に共感や内省といった深い感情の働きを経験しています。そして、それは「今この瞬間を大切にしたい」「限られた時間を味わいたい」という生き方につながっていきます。
花の命は短くて――と、古来多くの人が詩に詠んできました。でも、その短さゆえに、私たちは美しさをより深く感じ、人生について考えるきっかけをもらっているのかもしれません。
引用文献(抜粋)
• Ishizu, T., & Zeki, S. (2011). Toward a brain-based theory of beauty. PLoS ONE, 6(7), e21852.
• Keltner, D., & Haidt, J. (2003). Approaching awe, a moral, spiritual, and aesthetic emotion. Cognition and Emotion, 17(2), 297–314.
• Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: holistic vs. analytic cognition. Psychological Review, 108(2), 291–310.
• Kahneman, D., Fredrickson, B. L., Schreiber, C. A., & Redelmeier, D. A. (1993). When more pain is preferred to less: Adding a better end. Psychological Science, 4(6), 401–405.